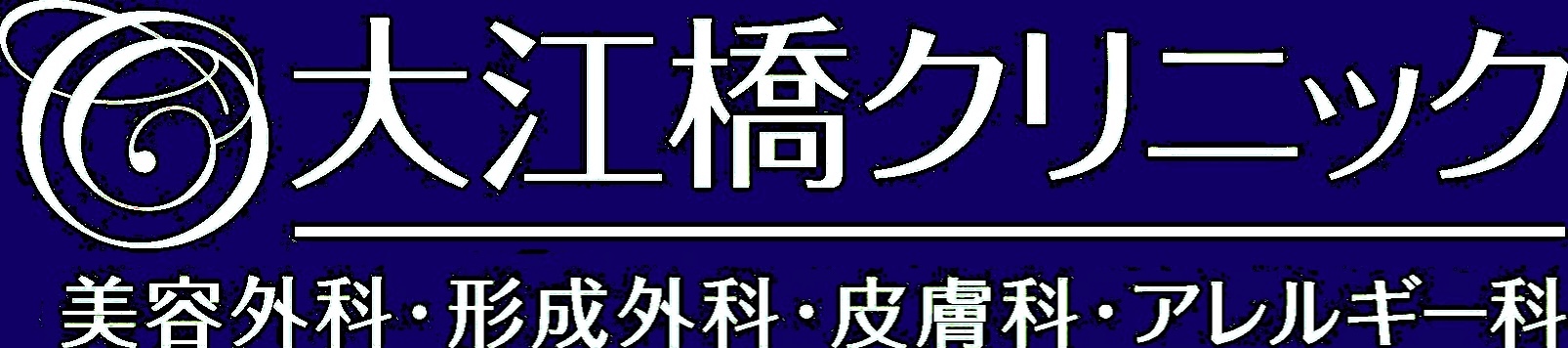※ 基本的な考え方は、以下のリンク先をご覧ください
見た目の改善を目的とする治療は保険適用できません ▶︎
〇〇の治療を保険でできますか、というお問い合わせを大変多くいただきます。日本の保険診療は治療費が諸外国に比べて大変安く抑えられており、保険証があればさらにその1〜3割を負担するだけで、後の7割は直接支払わなくて良いのですから、安く治療したいと考えている方にとっては魅力的な制度です。
しかし大江橋クリニックが主に行なっている見た目に関わる(すなわち美容的な)分野の治療は通常健康保険の適応になりません。
保険医療は互助的な仕組みに基づいた最低限度の「社会保障」です。命に関わる深刻な病気の場合などの場合、非常に高額な治療に健康保険が適用できるかどうかは重要ですが、保険の目的は病気などによって損なわれた健康を、再び働いて社会貢献ができる程度に、あるいは社会に大きな負担をかけない程度に回復させようというものです。治療目標は個人の満足ではなく、できるだけコストをかけずに日常生活を可能にすることです。医薬品も検査も治療法も、品質や快適性よりも価格が優先されます。
国民皆保険制度は弱者救済制度です

日本では「国民皆保険」と言って国民のすべてがいずれかの健康保険組合に加入し、保険料を支払う義務を負っています。保険料は従業員を雇っている会社も負担しており、集められた保険料で足りない分は国からの繰入れ等も加えてプールされ、保険診療を行なう医療機関や薬局等の請求に応じて支払われます。それは社会の負担を軽減するために用いられるべきで、個人の健康増進や美的改善の目的で用いる財源ではありません。
保険は保険料を支払っている人も利用できますが、原理的には保険料を払える(=健康で仕事をしている)人は通常あまり使用せず、保険料の負担に困難を感じる(病気で働けない)人に対して手厚くなるようなシステムです。
保険適応のない治療に健康保険を用いることは、本来の目的を逸脱した窃取にあたり、日本の保険制度を危うくするものです。保険医療は本当にそれを必要とする人に使ってもらい、自分の美と健康を守る医療は自分でその費用を負担しましょう。
本来、医療は自由診療であるべきです
自由診療の「自由」とは、その内容も、かかる費用も、患者さんとクリニックとの契約によって自由に決めてよい、という意味です。患者さんは、その費用を負担する意思さえあれば「医療の内容や質を選択する自由がある」といってもよいかもしれません。安くなるからと最低限度の医療水準に我慢する必要はないと思います。
しかし、一方で「診療」である以上医学的に根拠のない方法や、社会通念上認められないような医療(例えば、健康や命を損なうことを目的とした医療や治療効果のない詐欺的な医療)は行ってはならないでしょう。
私たちは、美容診療は「未病」を健康に近づける予防医学ととらえ、リーズナブルな料金でより健康で美しく過ごすための手段を、医学的な検証を行なった上で、適切に提供していきたいと思っています。
健康保険は医療保険ではありません
健康保険制度・国民健康保険・社会(健康)保険 などについて
日本における健康保険制度は、一般的な意味での「保険」ではありません。
自分の意思とは関係なく、職業と収入に応じて支払うべき保険料が決定され(国民すべてに健康保険加入が義務づけられています=国民皆保険制度)、そのお金は現在病気にかかっている他人のために使われます。自分の将来のために前もって積み立てておくことはできません。掛け金に応じた保証があるわけでも、後日払い戻される貯蓄でもありません。
病気になったときに健康保険に加入していない人は、それまでにいくら多額の保険料を払い込んでいても、保険治療は受けられません。
自分が病気になったときにも医療は支給されますが、健康保険の適応は厚生労働省が決定した基準に従って全国一律に決められており、適応のないものに対しては支払われず、適応条件は細かい注によって規定されています。また保険料を多く支払った人に手厚い治療が行なわれることはありません。支払った額に応じてリターンが得られるという保険ではないのです。
診療内容は診療した医師が恣意的に決めるわけではなく、医師ができることは症状を診断して適切な病名をつけ、病名に応じて定められた診療項目を選んで施行し、診療録に記録することだけです。
少しでもよりよい治療を、と望んでも国が認めた「給付」の枠から外に出る事はできません。それは、健康を保つ上での「最低限度の」治療であり、決して満足のいくものではありません。
ではもっといい治療を受ける事はできないのでしょうか?
そんなことはありません。保険を使わなければ、誰でも好きな医療機関と自由に医療契約を結び、最先端の治療を好きなだけ受けることができます。
それが「自由診療」です。あなたが医療費を自分で全額負担する決心をすれば、煩わしい制限は一切なくなります。
保険医療は現物支給です

保険診療は「現物給付」という考え方で医療が行われています。
あなたの加入している健康保険組合があなたに保険証(保険医療の引換券)を発行し、あなたはそれを「保険医療機関(保険医療の代理店)に持って行って「治療を給付して」もらいます。
保険組合は(医療機関でないことに注意!)あなたに「治療法とそれに用いる薬など」をセットにして医療機関を通じて給付します。医療機関はその際の「代理店」に過ぎませんから、診断に基づいて「病名」を決定したら、病名に対応した治療しかすることができません。保険が利かない、とは、あなたの保険者があなたにその医療(医療「費」ではないことに注意)を支給しないという意味です。
あなたが窓口で支払っている医療費の「一部負担金3割」とは、保険者(保険組合)が医療を支給する際にそれに要する費用の一部としてあなたから徴収している費用で、医療機関は保険者の代理店として、取り扱い手数料なしでかわりに収納し保険者に納めます。一方、保険者から医療機関へ支払われる「診療報酬」とは、医療機関が保険者に代わって患者さんに「医療を現物給付」したことに対する対価(原価および手数料)です。実際には、これらを相殺して、保険者から医療機関へは、「一部負担金3割」を差し引いた、診療報酬の7割分が審査を経て2ヶ月後に支払われます。
すなわち、本来ならば(現在窓口で支払っている自己負担金が、本来の徴収者である保険者に直接支払われるならば)、保険者(保険組合)は保険料でまかないきれない医療費をあなた(患者さん)から徴収して、医療機関に患者さんを(当座は無料で)治療させ、その経費を後ほど医療機関に支払う、という流れになります。患者さんは医療機関には治療をしてもらうだけで、支払は患者さんの属する保険組合にしているのです。
繰り返しますが、医療機関は患者さんから直接治療の対価として支払いを受けて診療しているのではなく、診療に要した費用は保険組合に請求し支払いを受けています。患者さんは保険組合から医療を支給してもらい、保険料から医療機関に実際に支払われる額との差額を医療機関に納めます。郵便局の窓口で税金を納めても、税金を郵便局に支払っていると思う人はないでしょう。税金は郵便局を通じて国庫や市町村に送られ、そのおかげで公共サービスが受けられます。あなたが医療機関の窓口で支払う医療費自己負担分は、医師の収入ではなく保険組合からの賦課金です。
患者さんに支給されるのが医療(現物)であって医療費でないことを示すため、支給される医療は点数化され、明細書には点数が記載されます。現在は1点が十円として換算されるため、3割負担の患者さんは1点を三円として計算し十円単位で五捨六入(四捨五入ではない)した金額を支払うことになっています。
健康保険の原則

健康保険の原則は、全国どこでも同じ値段で同じ治療が受けられる事です。
ですから保険診療には一部の施設でしか行えない「最先端の治療」や「特殊な治療」は含めてはいけない事になっています。また保険診療では医師の技量による値段の差は認められません。良くいわれる事ですが研修医でも教授でも手術料は同じなのです。
ここから出てくる解釈として、「どこの医療機関にかかっても保険診療である限り治療結果は同じであるべき」と考えられるので、保険診療ではたとえば遠方の名医をわざわざ受診する「必要は認められず」、他の医療機関よりも(薬の種類が多い、受診回数が多いなど)高額のお金がかかる治療をすることは「濃厚診療」として禁止されます。
言い換えるならば、他人よりよい治療を受けたい、という願望は「保険診療では許されない」のです。
以下に、患者さんが知っておくべき保険診療の原則をいくつか示します。
- ※ (マイナ)保険証の提示がなければ、保険診療を行なってはならない
(後日お持ちになった場合の払い戻し等は医療機関独自のサービスです) - ※ 同じ病気に対して、保険と保険外の治療を併用してはならない(混合診療の禁止:特例あり)
(保険外を併用する場合は原則的に全額自費になります) - ※ 同じ病気に対して、同時に2カ所の保険医療機関を受診してはならない
(どちらか1カ所の診療費は自費になることがあります)
※ セカンドオピニオンは原則的に自費となります - ※ 病名に対して認められた薬だけしか処方してはならない。特殊な治療法は行なってはならない。
- ※ 直接診察をしないで薬を処方したり診断書を書いたりしてはならない
(窓口でお薬のみを受け取ることは法律違反です)
健康保険の制約
最近特に、医療費削減の名目で保険診療に制限が多くなってきました。
使える薬の種類や処方期間の制限だけでなく、医師が診察の際に必要と考えて行なった検査・処置なども、後から審査して不必要・過剰であったとして保険者(支払い側)から支払いを拒否される事もあります。実際に行った診療について後から支払いを拒否された場合、それは当然医療機関の損失となりますが、それだけでなく、審査した支払い側の目からは必要のない医療を勝手に行い費用を過剰に請求した「医療機関の不正請求」ということになり、今後はより厳しく審査しようという姿勢になりますから、今後の保険診療に支障を来します。
また例えば、同じ病気について同時期に2つ以上の医療機関を受診した場合、一つの病気なのに治療を2回したことになりますから、その一方に対してしか医療費が支払われないことになります。
こうした場合、あらかじめ転医(前医の治療を中断して診療機関を変更する手続き)のための紹介状等をお持ちいただかないと、保険証があっても保険診療が行なえません。前の医者には「一度しかかかっていない」とおっしゃる方がいますが、その場合「前医での治療は継続中であり終了していない」と見なされます。
セカンドオピニオンは自費です
ご存じない方もありますが、セカンドオピニオン(別の医者の意見を聞く場合)は前医からの紹介状(治療データを含む)を御持ちいただいた場合でも原則として自費になります。2カ所で診察を受ける場合、2カ所目は自費、とご理解下さい。
また、同じ薬を、適切な検査をせずに数ヶ月以上にわたり延々と処方することは非常に難しくなりました。治療を継続する必要性を証明できないからです。
再発予防は「保険治療」の目的ではないため、投薬は短期にとどめ、治癒しないのならば治療法を変更するか中止すべきだと、保険者(支払側)は考えます。治癒しない疾患に延々と同じ薬を処方することは、「月余にわたって漫然と(必要な検査や治療効果の判定をせず)投与してはならない」という規定にかかるので、医療機関は処方を打ち切るか他の薬に変更しなければなりません。再発した場合は治療再開できますが、治らないもの(傷痕や色素沈着などの病気の後遺症ともいえるもの)は原則的に保険では治療できません。
また、実際に行った治療の内容や費用についても、保険者側が再審査し、後日、適応外治療であったとして変更・減額してくる可能性があります。
例えば、同時に2つ以上の手術(黒子を二つ取るなど)を行なった場合、その一つに対してしか費用が支払われない場合や、同一の治療を短期間に繰り返したときに2回目以降の保険適用が認められない場合など、特に理由が明記されていない(その他の事由、などと記載されている)のに保険適用が認められない場合が多々あります。
大江橋クリニックではこうした場合、保険適応を取り下げ、健康保険から自費診療への変更をお願いすることもあり得ますので、ご協力をお願いいたします。
診療報酬という名称に対する誤解
診療報酬はマスコミ(特に悪質なのは日本経済新聞や朝日新聞)で喧伝しているように全額が医師の収入ではありません。(日本経済新聞などが、診療報酬イコール医師の給料、であるかのような記事を載せることがたびたびあります。明らかに悪意ある嘘です。)
診療報酬には医療用の材料費、薬剤費、医療機関の運営経費と消費税が含まれていますので、その大半は薬代や材料費、家賃や光熱費、職員の人件費として医療関連の会社や医師以外の職員への支払い等に充てられ、医療機関の実際の収益は支払われた医療費の数%にすぎません。人件費率も他の業種に比べて低く抑えられています。
従って、保険者側の恣意的な支払い拒否は、たとえ少数少額であっても医療機関の存続を危うくするものです。保険診療には様々な制約があり、その制約の中で患者さんの利益が最大になるように、各医療機関は努力を続けています。
健康保険の適用にならない事例解説

「瘢痕拘縮形成術」の対象にならない傷跡
健康保険の適用条件として医療機関が参考にするのは、原則2年に一度改訂される診療報酬点数表です。
けがや手術の傷痕を保険で治したいというご希望は大変多いのですが、傷跡をきれいにする治療は美醜(見た目)に関わるので美容治療です。例外として「運動制限を伴う」ような高度な瘢痕であれば「瘢痕拘縮形成術」の対象となり、健康保険で治療が受けられることがあります。しかし傷痕が大きく醜いものであったり、長期間消えずに残り、もっときれいに治したいという場合でも、運動制限を伴わない場合には傷跡治しの手術は自費になります。
拘縮とは傷が引き攣れているという意味で、引き攣れを伸ばす事で「運動制限を解除する」すなわち関節などを動きやすくする場合に限って保険が使えることになります。
ですから顔面の「瘢痕拘縮形成術」は瞼や口などが開かないような場合に限って認められ、額や鼻などのように本来動かない場所は、いくら傷跡が目立ったとしても運動制限がなく保険適用は認められません。その他(顔面以外)の場合も同様に、通常は関節部分が拘縮して曲げ伸ばしできない場合に限られ、その他の部位(腕や脚、背中など)の傷は認められないのです。
耳の変形を整える手術
大江橋クリニックで専門的に行なっている手術です。
健康保険の耳介形成術は注(厚生労働省通知:実施上の留意事項について)がついていて「耳輪埋没症、耳垂裂等」に対して行なった場合に算定する、と書いてあります。その他の耳介の変形については何も規定がなく、普通に読めば保険適応はありません。
「耳輪埋没症、耳垂裂等」以外の耳の変形が健康保険の適応とは見なされないのは、社会生活上著しく不都合とまでは言えない、自己責任である、「耳の機能」と密接な関係にないなど、「耳の形」の修復が「美容的な問題」と見なされるためだと思われます。
機能的な意味の「耳介形成」とは、メガネやマスクをかけられるようにする、あるいは耳の聞こえをよくする(例えばイヤホンや補聴器が入るようになる)ために行うものと考えると、保険適応の有無が理解しやすいのではないでしょうか。
なお耳垂裂とは、生まれつき耳垂(耳たぶ)が丸い形に整わず、2つに裂けたように見えるものを言います。正常側に比べて耳たぶ自体も一部が欠損したように小さいものが多いようです。日本形成外科学会の定義によれば「生まれつき耳垂が割れている状態の耳介先天異常の一種」とあり、ピアスによる耳切れなど外傷性の後天的なものは含まれません。
※ 厚生労働省の関連機関である近畿厚生局に問い合わせた結果も、ピアスによる耳切れは適応外である旨の回答をいただいており保険適用はできません。事故や暴力等による場合は別の理由(別に加害者がいる場合は健康保険の対象にならない)で保険適応となりません。したがってピアスの耳切れ等は自費となります。
外傷などの結果軟骨が著しく変形した場合でも、耳の機能(音の聞こえ方)に問題がなければ見た目の改善目的になります。
柔道耳など激しいスポーツの結果生じた変形の場合には自己責任の範疇であるともいえます。ピアスの穴が裂けた場合も、原因がピアスを付けた事により生じているので自己責任です。
ピアス部に生じたケロイドや腫瘍などは、ピアスが原因とはいえできもの(病気)ですので切除そのものは保険でできるようです。しかし切り取ったあとに大きな変形が残っても、それを治す手術は「耳介形成手術」の対象にはなりません。
他院で立ち耳等を保険診療しているとの指摘について
他の医療施設で保険で行っているとの情報は多々耳にします。中には耳の角度によるなどと記載しているところもあります。しかし立ち耳(聳立耳)は耳介形成手術の対象になっていませんから、耳輪埋没症などの病名を便宜的につけて、いわゆる保険病名(保険を適応するための偽の病名)による保険適応としているのではないかと思われます。別病名をつけて治療した場合、医師の好意とはいえ「診療報酬の付け替え請求(本来保険請求できない処置を、別の病名や手術名に付け替えて請求する)」という違法行為となり、悪質と判断されれば保険医取り消しなどの処罰もある行為となります。
※ 都道府県によっては立ち耳の手術を健康保険で行えるところもあるようですが(北海道など?)、大江橋クリニックで近畿厚生局に確認したところ、立ち耳修正は美容手術であり保険適応がないという答えでした。あるいは大学病院や公立病院などでは、医師の知らないところで事務が処理しているのかもしれません。(基本的に自費診療を行えないことになっている病院もあり、自費診療すべき治療を保険扱いにしているケースもあります。)
瞼がたるんでいるが「眼瞼下垂症」ではない場合
加齢とともに瞼の皮膚は徐々に伸び、たるんで睫毛の上に被さるようになってきます。これは眼瞼下垂でしょうか。
眼瞼下垂症は、眼瞼挙筋の働きが低下して起こる視野障害をさすのが本来です。
加齢による皮膚の延長の場合は筋肉の働きは損なわれていません。眼瞼挙筋機能が正常であるため、皮膚を減量すれば視野は保たれます。皮膚切除は美容手術として行います。
眼瞼挙筋腱膜が瞼板から離れて上方に変移していることが明らかな場合「腱膜性」眼瞼下垂症として保険で扱うのは許されるでしょう。
眼瞼下垂症手術は、挙筋前転法または吊上げ法で行なうのが普通ですが、「その他の術式」という項目もあるため、皮膚切除などが許されないわけではありません。
しかし眼瞼挙筋の働きが正常な場合は、そもそも眼瞼下垂症ではないので「老人性皮膚弛緩症」などと名付けて自費でシワとり手術を行なうのが一般的です。
また糸で行なう埋没法のようなミュラー筋タッキングや皮膚切除のみの場合は「眼瞼挙筋前転法」を適用する事は難しいと思います。
挙筋前転法には皮膚切除は含まれないとして、皮膚切除は「自費」で同日に別途請求する医療機関もありますが、本来これば「混合診療」にあたり健康保険制度のもとでは認められないと思われます。
タルミ取り手術は「美容」ですから本来は全額自費になります。
二重の幅を何ミリと要求される方がいますが、これは見た目の改善目的で美容の範疇となり保険適応の手術では要求に応じるべきではないでしょう。もちろん「自然に」「控えめに」程度のお話であれば整容的な努力はするべきですが。
エステで脱毛治療を受けてやけどした
いわゆるエステティックサロンなどの施術業者は、脱毛やしみとり、アートメイクなど人体に傷害を与える可能性のある行為を行なう事が禁じられています。違法行為の結果傷を負ったという事なので、加害者には傷害罪が適用されますし被害者には加害者に損害賠償請求する権利があります。
「第三者行為責任」という方法で保険診療を受ける事も不可能ではありませんが、この場合ご本人から保険者に賠償請求権が移り、後あと非常に困る事があります。(これを逆手に取って「すぐ保険で診てもらうように」言って被害者本人との賠償交渉を避けようとする場合もありますので、注意が必要です。)
明らかに事件性のある場合だけでなく、マッサージを受けたらクリームにかぶれた、などの場合も施術業者に行為責任があると考えられますので、保険診療の扱いをしない様にしています。本当にかぶれが原因かどうかの特定は難しいため、保険診療を行なうと誰が誰にいくら支払うべきかについてもめる場合があるためです。